東京アートポイント計画通信
東京アートポイント計画は、地域社会を担うNPOとアートプロジェクトを共催することで、無数の「アートポイント」を生み出そうという取り組み。現場レポートやコラムをお届けします。
2013/11/22
熊谷POレポート アートプロジェクト考察日記(その6)
「記録するための方法論をさぐる:映像編」
アートプロジェクトの現場では記録を残すために、いくつかの方法が試されていますが、そのひとつの手法として、映像記録が残されます。ところが、残念ながらその記録が編集や公開されたりすることは少なく、有効活用されることは少ないと言えます。
言わば、現場でしか感じられない何かを残したいという思いはあるにもかかわらず、方法論がわからないので、とりあえず映像をとっているという状況です。その結果、残った映像は、資料として内部スタッフ及びステークホルダー間で共有されるにとどまることが多いのです。
ところで、折角残った映像が有効活用されないのは、何のために映像をとるのかという目的意識が定まっていないからでもあります。「アートプロジェクトの現場」を残したいという思いを結晶化するためには、ただやみくもに映像を取るのではなく、事前あるいは事後に「その映像で何を残したいのか」「その映像に何を残したいのか」を考える必要があるのでしょう。そのため、現在、Tokyo Art Research Labではアートプロジェクトの現場を残すための手法開発のための研究を行っています。(映像記録についての佐藤さんの記事や音の記録についての長尾さんの記事を参照のこと。)そして、アートプロジェクトの現場で映像を取る手法は手探りながらも、いくつかのパターンが生まれつつあります。
①プロの撮影スタッフ(あるいはある程度のスキルを持ったチームを編成し)が映像を編集し、ハイライトを集めたダイジェスト版を作成することを目的とするもの。
②ボランティアや様々な参加者などがアマチュアレベルではあっても、映像を記録しデータを集積させるもの。
③もっと単純なレベルであれば、イベント開催中定点カメラで全てを録画するというもの。
それぞれの記録手法には長短があります。例えば映像としての質が高いにもかかわらず①は、現場の空気を伝えるには不向きです。そのため、現場スタッフは特に、プロジェクト独特の空気感が残っていないと残念に思うことが多いようです。プロジェクト自体が見るためのものではなく、体験されるべきものであった場合、一方向のディレクションで映像を編集することは、おそらく体験にとってとても重要な要素を取りこぼすことになるでしょう。
また②のように映像一つ一つが特別に鑑賞されることを目的としていない場合、第三者が映像を見ても、その性質がわからず、映像自体がプロジェクトの情報を伝えない場合もあります。昨年度この手法を追求し「フネタネスコープ」という手法が開発されました。
この手法では一分間、定点、ズームなしの映像を、プロジェクト参加者が思い思いに取ることにより、複数の観点からの記録が大量に残るしくみがデザインされました。この映像は単なる記録にとどまらず、「つどい」という会を設け、関係者同士で鑑賞することにより埋もれた記憶を掘り起こす装置としても機能します。この手法は佐藤さん曰く、「なんとなく」記録する、つまりは映像記録のハードルを下げる手法でもありました。一方で、アウトプットを映像として活用することを前提とはしていなかったため、ここからプロジェクトがもっていた雰囲気などを感じてもらうためには、展示、あるいはデジタルアーカイブとして改めてデザインを加える必要がありました。そこで採用されたのは、他画面で同時に映像を見るという手法です。そして不思議なことに、よく似通った手法が全く別のプロジェクトの現場でも採用されました。その例を次に取り上げます。

種は船⇔船は種 ドキュメント展 in 舞鶴(2013年1月19日(土)~3月3日(日)、監修NPO recip/一般社団法人torindo)
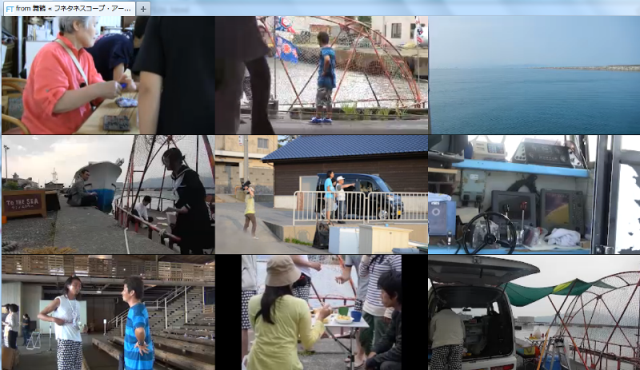
フネタネスコープ デジタルアーカイブ画面(現在公開に向け準備中)
この奇妙な記録映像のアウトプットの類似が生まれたのは、長島確さんを中心に製作されたプロジェクト「豊島区在住アトレウス家」を、映像エンジニアである須藤崇規さんが撮った記録映像の上映の際です。10月6日(日)に行われたTARLの「リサーチプロジェクトの検証:記録=共有の手法を探る」第2回 公開研究会ではその記録手法とアウトプット方法について取り上げられました。再演と位置づけられた上映会では、豊島区で実施された「アトレウス家」の映像が上演されました。会場では公演当時の状況をなるべく再現するとともに、一つの部屋では定点で公演時間中に撮影した映像が6面分割で同時上映されました。これは③の例でもあります。

アトレウス家再演の一室
不思議なことに、打ち合わせ時に長島さんと須藤さんから多画面映像を見せてもらった時と、空間構成され再演された映像を見た時には受ける印象が全く違いました。端的に言えば、鑑賞者として映像への没入度が全く違い、この参加の度合いのデザインこそが、アートプロジェクトの記録のデザインの仕方に大きく関わってくるのではないかと感じられました。
このように、リサーチのドキュメントとしての映像/展示、映像のデジタルアーカイブ/インターネット上での公開、演劇の記録/公演など、アウトプットの場は違えど、それぞれで多画面を同時に鑑賞するという手法が選択されました。ある種の方向性を持たない映像のアウトプットの解決方法の不思議な一致には、映像の編集者や鑑賞者のスタンスの変化にも影響されているのではないかと思われます。
その映像が存在する空間は物理的な現実の空間の場合と、バーチャルのインターネット上の空間などと様々ですが、共通するのは映像が現場の空気を伝えるためには、映像だけではなく、その環境を再現することも求められていることです。映画館のようなニュートラルな空間と比較してみれば明らかですが、これまでの例では、一方的に映像を上映するだけではなく、その空間も含めて再編集するということが行われたと言えるのではないでしょうか。これはアート作品の展示空間がホワイトキューブのようなニュートラルな空間から、アートプロジェクトへ展開するに際し、まちなかで文脈を背負ったこととも呼応しています。そしてアートプロジェクトという展開する際に文脈を不可欠とするアートの有り様を記録し、アウトプットするために、何らかの形で文脈を付与するための仕組みが考案されるのは、不可避なことだったのかもしれません。
また、記録映像の性質の変化は観る側のスタンスの変化にも微妙に対応しているようです。例えば、鑑賞者の側も映像に完全に没入し見るというよりは、もっと「なんとなく」映像を体験します。私たちの日常では、パソコン上でいくつも画面を開き、作業を同時進行することが当たり前になっています。今を生きる私たちは、無意識のうちに、このようなマルチタスクのチャンネルを体内に備えているのではないでしょうか。もちろん、複数の作業を同時進行していても、意識の集中度合いの加減はなされています。この集中していない状況のコントロール、あるいは集中せずとも楽しめるインターフェースの開発こそが、アートプロジェクトの記録とアウトプットの手法に求められているのかもしれません。
これまで見てきたように、記録やそのアウトプットのデザインは、すなわち人々の意識をデザインすることでもあるようです。意識/無意識の境界で場の空気をも記録し、伝えること。そして、空気を伝えるための環境を設定すること。困難ですが、とても面白いことが進行していると手応えを感じました。
東京アートポイント計画 プログラムオフィサー 熊谷薫

