東京芸術文化創造発信助成【長期助成】活動報告会
アーツカウンシル東京では平成25年度より長期間の活動に対して最長3年間助成するプログラム「東京芸術文化創造発信助成【長期助成】」を実施しています。ここでは、助成対象活動を終了した団体による活動報告会をレポートします。
2021/02/17
第10回「映画表現としてのライブ・パフォーマンス」
〜プロジェクト「音から作る映画」と連続講座「映画以内、映画以後、映画辺境」を振り返る〜
対象事業:チャーム・ポイント「音から作る映画の展開と完成・公開」(平成27年度採択事業:3年間)
スピーカー(報告者):
七里圭(チャーム・ポイント代表、映画監督)
高橋哲也(チャーム・ポイント副代表、ムービーカメラマン)
棚沢努(チャーム・ポイント会計、映像ディレクター/プロデューサー)
司会進行:今野真理子・碓井千鶴(アーツカウンシル東京 企画助成課 美術・映像分野担当シニア・プログラムオフィサー)
助成対象活動の概要
映画制作の通常プロセスを逆転し、音(サウンド・トラック)から作り始めることで、映画という表現形式に組み込まれた他ジャンルの諸要素をアンパッキング。それらを映画と比較・検証しながら、再構築することで映画制作を行った。よって、電子音楽やボイス・パフォーミング、ダンスや演劇、美術など様々なジャンルのアーティストとのコラボレーションが、ワーク・イン・プログレスとして発表された。その活動は、ライブ・パフォーマンスと映画制作の往還となり、3年の助成期間に、4本の新作上演作品および5本の劇場公開映画(長編)、2本の短編映像作品に結実し、海外のフェスティバル参加も実現した。また並行して、関連するテーマについての連続講座「映画以内、映画以後、映画辺境」も多彩な論客を招いて11回催し、その議論を制作にフィード・バックするとともに、最終年度には総勢8名のゲスト・パネラーが登壇してのシンポジウムを二夜にわたり開いた。
レポート
プロジェクト「音から作る映画」と連続講座「映画以内、映画以後、映画辺境」は、映画監督の七里圭と、フリーランスの映像スタッフ、音楽家、美術家らで結成されたグループ、チャーム・ポイントが、パッケージとしての「映画」に留まらない表現の可能性を求め、2013年にスタートさせた企画です。歴史や技術の変遷、観客との関係など、さまざまな観点から「映画」を捉え直す講座を開催し、そこで見出された視点をライブ・パフォーマンスや実際の映画制作へと展開していくプロジェクト。のべ5年にわたる活動を見渡す報告からは、併行する2つの企画がおりなす有機的な関係に加え、創造と思考が絡み合いながら、さらなる創造を引き出していく様子が、生き生きと伝わってきました。
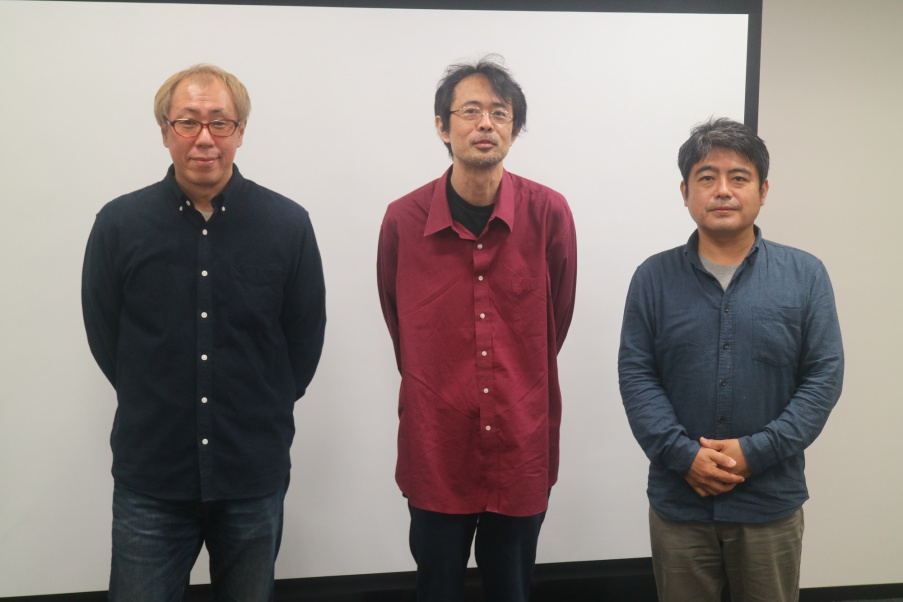 (左から)棚沢努さん、七里圭さん、高橋哲也さん
(左から)棚沢努さん、七里圭さん、高橋哲也さん
映画のワーク・イン・プログレス(2013・14年度/単年助成)
デジタルで撮影、編集され、公開あるいは配信される「映画」は、これまでのそれと同じものなのだろうか。プロジェクト「音から作る映画」と連続講座「映画以内、映画以後、映画辺境」は、デジタル化をめぐり「なんだか映画が映画じゃない気がしてきた」という、七里圭の漠たる違和感を発端としてスタートした。長期助成の対象となったのは平成27年(2015年)からの3カ年。だが、企画自体は、さらに遡ること2年前から単年助成を受けて進行しており、2015年4月の時点で9回の講座が開催され、プロジェクトの出発点となるライブ・パフォーマンス、映画が制作されていた。講座では、フィルムにとどめられた光と影の痕跡からデジタル信号への移行、トーキー映画の登場以後の音との関係、オンライン配信やライブ上映などの視聴環境の変化といった、さまざまな論点が浮かび上がった。一方、実践編にあたるプロジェクトでは、講座で示されたテーマの中でも特に、通常の映画制作においては最後につけられる「音」を手がかりに、「映画とは」が紐解かれつつあった。
2014年4月のライブ『映画としての音楽』では、12人の出演者がオスカー・ワイルドの「サロメ」(日夏耿之介訳)を、スクリーンに投射される映像に合わせ、歌、台詞、叫びなどさまざまな手法で発声。いわば、サウンドトラックの実演(発声のタイミングは映像に組み込まれたサインによって厳格に指示されている)だが、スクリーン上に示されるのは、映画と音楽の出会いを擬人化した別の物語の字幕。視覚と聴覚が完全に重なり、統一される「映画」体験とは異なる空間がそこに立ち上がった。さらに、このライブ・パフォーマンスの音源をもとにつくられた映画『映画としての音楽』(2015年4月公開)もまた、映像としては字幕と風景のみの、多様な声、言葉が錯綜する作品だった。これら『映画としての音楽』シリーズを、七里は「ワーク・イン・プログレスの発表」と振り返る。「美術や演劇では普通に行われているワーク・イン・プログレスですが、それを映画制作に取り入れたらどうなるか実験してみたんです」
「ドキュメント 音から作る映画」より抜粋
「映画」を脱ぎながら、「映画」をつくる(〜2015年度)
「完成=終結」を前提としない「進行中」の実験は、さらに展開を遂げる。2015年2月に、複数のスピーカーを用いて電子音楽を演奏し立体音響空間を立ち上げる「アクースモニウム」の手法を使って上映された『サロメの娘』は、既存のフィルム映画としてのそれとは異なる「サロメ」を志向し、構想、命名された作品。新柵未成が書き下ろしたオリジナルのテキストをもとに、檜垣智也がミュージックコンクレートを制作、それをもとに映像をつくる、という流れは、先行する『映画としての音楽』とも共通するものだ。「逆からつくることで既存の映画をアンパッキングする。デジタルの時代だからこそ、映画に組み込まれてきた、さまざまな要素を並列に取り出した」と七里。長期助成の初年度にあたる2015年の8月にはフランスの国際電子音楽祭FUTURAで『サロメの娘』のアクースモニウム上映を行い、翌月には「音から作る映画」シリーズと連続講座のこれまでを記録した『ドキュメント音から作る映画』を公開。さらに歩みを進める形で『サロメの娘 アナザサイド(in progress)』にも取り組んだ。これまでに発表したサウンドトラックに、コンテンポラリー・ダンサーの黒田育世、神村恵とのコラボレーションを交え制作した同作では、電子音と弦楽器、複数の女性の声からなる響きが、曖昧で断片的な記憶、自然、馬、踊る身体といった映像と共に、複雑で豊穣なイメージのうねりをつくりだしていた。
「サロメの娘 アナザサイド(in progress)」予告編
「映画」はどこにあるか。拡張する実験(2016・17年度)
「フィルム時代の映画は『サロメ』なら『サロメ』、『サロメの娘』なら『サロメの娘』と、基本的には一つしか存在しないものです。でも、デジタルはデータの集まりですよね。それが一つのパッケージだけに収まること自体が不自然なのではないか」(七里)。長期助成の1年目を終えて掴めてきた方向性は、ひとつの解答に向かって思考を収斂させるのではなく、むしろその問いや取り組みを拡張していくような活動のあり方だったようだ。2016年度には身体表現、ライブ・パフォーマンスと上映とのコラボレーションを軸にプロジェクトを展開。多摩美術大学での試演会を経て、原宿VACANTでの「音から作る映画のパフォーマンス」を開催した(2017年2月)。『サロメの娘』のパフォーマンス版、アクースモニウム版に加え、『映画としての音楽』のインターナショナルバージョンである『Music as film』の上映を、3日連続で、客席や舞台のセッティングをも変えて行う同企画は、これまでの試みを一堂に集めて検証する場であり、また、翌月公開されたあらたな作品『アナザサイド サロメの娘 remix』の撮影現場ともなった。
第1日「サロメの娘/パフォーマンス」
第2日「サロメの娘/アクースモニウム」
第3日「Music as film」
一つの試みが別の試みを呼び、時おり合流もしつつ併走し、さらに異なる試みを呼び寄せる—チャーム・ポイントの活動の本懐は、こうした動き方にこそあると言えるだろう。翌2017年度には朗読ライブと映像インスタレーションによる『サロメの娘』の上演に続き、同じテキスト、サウンドトラックを用いた新作映画『あなたはわたしじゃない サロメの娘 ディコンストラクション』を発表。一方、連続講座もライブ上演や上映、映画制作と併行して途切れることなく続けられ、2018年2月には、これまでの22回の内容やプロジェクト「音から作る映画」の流れをまとめた冊子『映画以内 映画以後 映画辺境』を発行、記念のシンポジウムも開催され、3年間の活動をいったん締めくくった。
思考と実践が絡み合う「運動」が開くもの
4本の新作上演作品、5本の劇場公開映画、2本の短編映像、14回の講座とそのアーカイブ冊子、シンポジウムと、この2本立て企画の残した成果には目をみはるものがある。それらはどれも、思考しながら動き続け、拡張を続けるチャーム・ポイントならではの活動形態なくしては生み出されなかったものだ。「デジタルという最新鋭の技術を使って、相当に手間のかかる、原始的なことをやっているんだと思います。映画が本来持っていた怖さ。七里さんはそれをもう一度獲得したいと努力している。そのことを支援いただいたことは本当にありがたいと思っています」と、メンバーの棚沢努はこの3年を振り返る。
彼らが掲げる、映画表現の可能性、怖さの再発見といったテーマは、観客動員数や海外公演の実施などの明確な指標とは異なり、ともすれば、抽象的で、つかみどころのないものにも思える。実際に、報告会で紹介された講座やトークでの議論にも、一筋縄ではいかない、難解さを覗かせるものが多かった。にもかかわらず、この取り組みが決して曖昧でない強さと吸引力を持つのは、そこでの議論や思考を、実に貪欲に、あらたな表現の創造へつなげているからだろう。また、そうした思考や批評と作品づくりが創造的な関係を結ぶ「運動」そのものに対し、助成が行われたことは、一つの団体の枠におさまらない、「映画」の支援にもつながるのではないか。冊子にまとめられた講座はもちろん、上映や上演、トークを記録した映像、そしてそれらを元につくられた作品群は、「映画表現」とは何か、その可能性を探求するすべての人に開かれた貴重なアーカイブとなるはずだ。
 制作された2つの冊子「映画以内、映画以後、映画辺境」、「清掃する女/音から作る映画/ベルリン・パリ公演『シネマの再創造』報告書2020」
制作された2つの冊子「映画以内、映画以後、映画辺境」、「清掃する女/音から作る映画/ベルリン・パリ公演『シネマの再創造』報告書2020」
(構成・文:鈴木理映子)
プロジェクト概要:https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/what-we-do/planning/strategic/44260/
チャーム・ポイント
映画監督の七里圭を中心に、フリーで活躍する映像スタッフ、音楽家、美術家、写真家、詩人等が、既存の表現ジャンルに留まらない作品を制作、発表するために緩やかに連帯し結成。映画表現を拡張する創作活動を続ける一方で、そうした志向を共有できる表現者や研究者、観客が連携するための場づくりにも力を注いでいる。これまで制作した映画に『ホッテントットエプロン-スケッチ』(2006)、『眠り姫』(2007)、『DUBHOUSE』(2012)、連作『To the light』(2014~)など。
【スピーカープロフィール】
七里圭
映画監督。1967年生まれ。早稲田大学卒。在学中から映画の現場で働き始め、約10年間の助監督経験の後、『のんきな姉さん』(2004)で劇場デビュー。その後、『マリッジリング』(2007)のような商業映画を監督する一方で、声と気配で物語をつづる異色の作品『眠り姫』(2007)を自主制作・配給。上映10年のロングランを機にサラウンドリマスター版(2016)も制作・公開。建築家と共作した『DUBHOUSE』(2012)が国際的な評価を受ける。近年は、「音から作る映画」プロジェクト(2014~)など実験的な映画作り、映像パフォーマンスにも取り組んでいる。2017山形国際ドキュメンタリー映画祭インターナショナル・コンペティション審査員。2018年よりWhenever Wherever Festivalのキュレーションも務める。多摩美術大学非常勤講師。
http://keishichiri.com/jp/
髙橋哲也
1966年生まれ。早稲田大学第一文学部卒後、映像制作会社、記録映画制作会社を経てフリーの撮影助手として映画、CM、ミュージックビデオなどの現場で経験を積む。助手の仕事と並行して、1998年七里圭監督のVシネマ作品にカメラマンとして起用されたのを契機に、その後インディペンデントな映画作品等で撮影を担当するようになる。七里監督との主な作品に『夢で逢えたら(2004)』、『眠り姫(2007)』、『マリッジリング(2007)』、『サロメの娘 アナザサイド(in progress)(2016)』。その他、高橋康進監督『ロックアウト(2008)』、岩名雅記監督『シャルロット/すさび(2017)』などがある。近年は暗黒舞踏の舞台記録映像を担当することも多いことから、徐々にカメラマンとしての活動にとらわれない、舞台表現への関りも深めている。
棚沢努
1968年生まれ。立教大学社会学部社会学科及び日本映画学校卒業後、映画会社シネカノン、映像制作会社ダブ勤務経験を経て、2006年よりフリーのディレクター/プロデューサーに。以降、様々な映像制作を手掛け、近年では映画の予告編(アピチャッポン『光りの墓』、『世紀の光』、ワン・ビン『三姉妹』、『収容病棟』、フー・ボー『象は静かに座っている』他多数)も積極的にディレクションしている。七里圭監督『眠り姫』ではプロデューサーとして、長年一緒に活動を共にしている。

